こんにちは、ヨーローです。
本日は、Jリーグを観戦する中で最近感じていることを、自分なりの視点で書いていきたいと思います。特に「守備」、そして「センターバック」というポジションにフォーカスして、今のJリーグがどのように変化してきているのかを考えてみます。
映像時代のJリーグ:勉強になる失点シーン
今やDAZNの普及で、試合結果はもちろん、得点・失点シーンや問題となったプレーの映像をいつでも見ることができるようになりました。これは本当にありがたいことで、選手にとっても学びの素材として非常に有益だと思います。
私自身も最近、センターバックとしてオーディションを受ける立場になったこともあり、失点シーンに特に注目して観るようになりました。「なぜこの失点が生まれたのか?」を自分なりに分析することで、守備の判断やポジショニング、連携の重要性を再認識させられています。
プロ選手であってもミスはする。だからこそ「どこでズレが生まれたか」「どうすれば防げたのか」を考えることが、ディフェンダーとしての成長に繋がっていると感じます。
変化するJリーグ:加速するショートカウンターと切り替えの速さ
近年のJリーグを見ていて感じるのは、攻守の切り替えが非常に早くなっているという点です。少ないパス数、例えば自陣から2〜3本でゴール前まで運ぶような、いわゆる「ショートカウンター」が多発しています。
一昔前は、横パスやビルドアップ中心で、いわゆる“中盤のファンタジスタ”が試合をコントロールするスタイルが主流でした。ボランチが起点となって華麗なパスやドリブルでチャンスを演出する、そんな時代です。
しかし、今は「走らなければレギュラーになれない」時代。複数人が同時に、全力で前に出ていくようなチームが上位に食い込んでいます。例えばセレッソ大阪や、私が今注目している京都サンガなどは、前からの激しいプレスと連動性のある攻撃が特徴的です。
■特に印象的なのは——
- ボールロスト → 即時奪回 → 縦パス → 複数人の走り出し → シュート
- この一連の流れが、数秒で完結するほどのスピード感
世界的にも稀に見るほど、ショートカウンターが洗練されてきているのではないかとさえ思えます。
京都サンガに注目する理由
今気になっているチームは、**京都サンガF.C.**です。サンガは近年、前線からのプレスとスピード感ある攻撃を武器に、戦う集団へと進化しています。
縦に速い攻撃、シンプルで力強いフィニッシュ。そこに日本人選手の技術の高さ、そして外国籍選手の決定力が融合して、非常に効率的かつ質の高いサッカーを見せています。
サンガの守備→攻撃への切り替えの速さや、複数人の連携したプレッシングは、ディフェンダー目線で見ても非常に参考になります。
フロンターレ・高井幸大選手にも注目
そして個人的に注目している選手が、川崎フロンターレの高井幸大選手です。
まだ若いセンターバックながら、落ち着いたボールさばき、ビルドアップ能力、ポジショニング、そしてフィジカルの強さを兼ね備えており、これからの日本サッカーを背負う存在だと思っています。
彼のプレーを見ると、守備の基本に忠実でありながらも、攻撃の第一歩を作れるようなCBがいかに重要かを感じさせられます。
守備の面白さを知ってほしい
今のJリーグ、攻撃サッカーが主流となっている中で、「守備を見る」ことの面白さも再発見されています。
ショートカウンターが多い今だからこそ、どこでボールを失ったのか、なぜ戻れなかったのか、どこにスペースができていたのかなど、守備側の視点から見ることで、より深くJリーグを楽しめると思います。
ショートカウンターが“悪”だとは思いません。ただ、こうして守備を観察することで、「もっと良くなる可能性」や「チームとしての穴」が見えてくる。
だからこそ、これからもJリーグを楽しみながら、特にディフェンスの視点から観察していきたいと思っています。
まとめると:
- 今のJリーグは“切り替えと走力”が命
- 京都サンガのような前からの守備が鍵
- 高井選手のようなビルドアップ型CBが重要
- 失点シーンの分析は最高の教材になる
これからも、Jリーグを守備目線で楽しんでいきましょう!
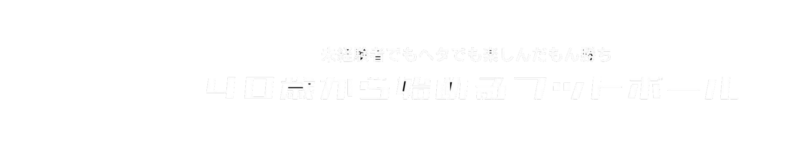



コメント